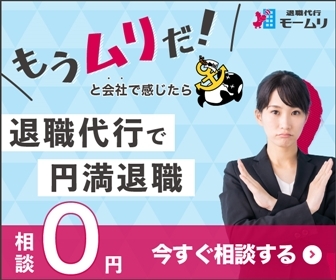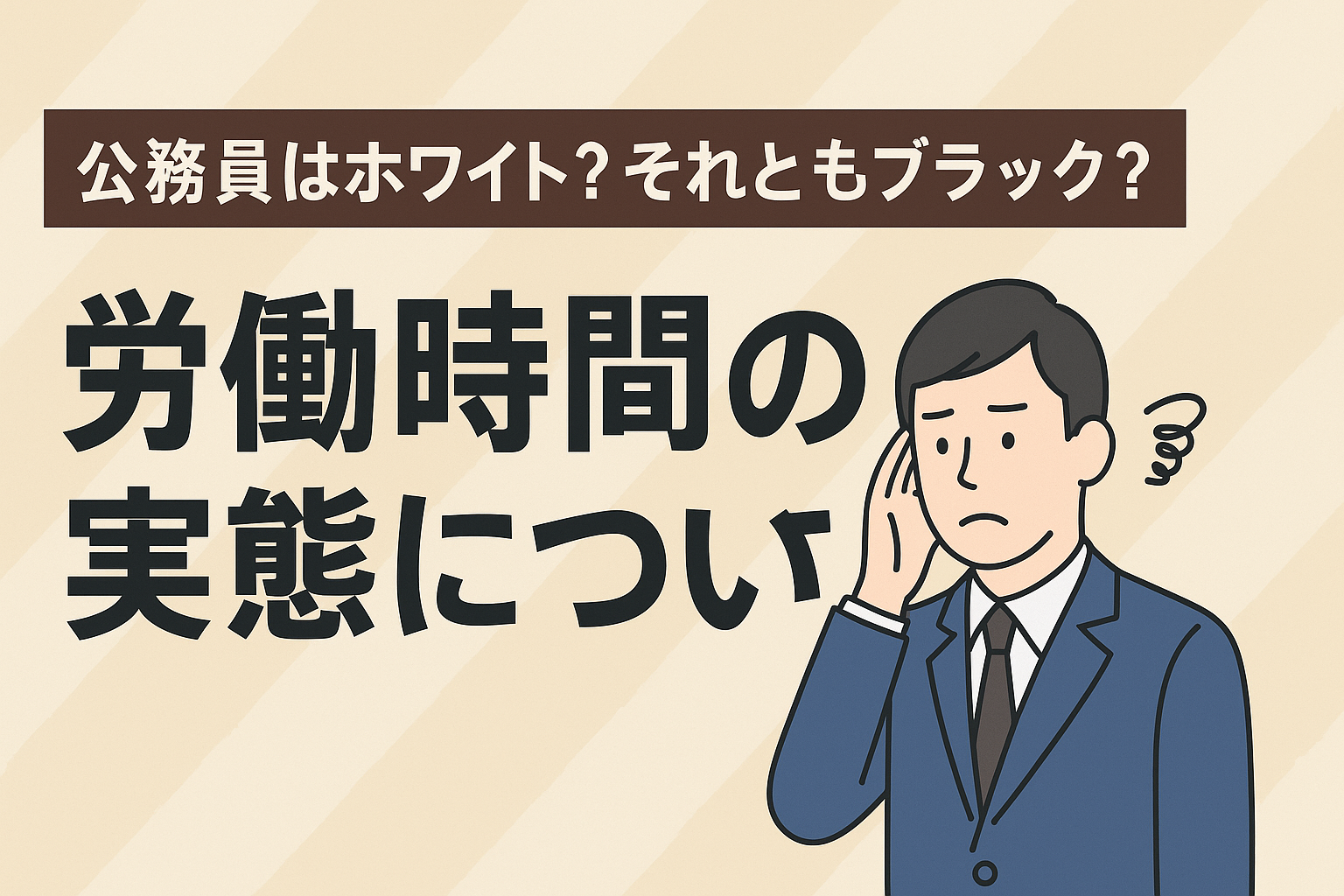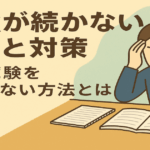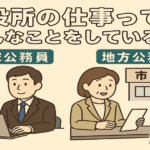「公務員=ホワイト」のイメージはどこから
公務員はなんとなくホワイトなイメージがある方が多いのではないでしょうか。実は私もその一人で、公務員になろうと思った理由の中に、「楽そう」「ホワイト」というものがありました。基本定時で上がり、休みはしっかり取れて、有給も取りやすい、そんなイメージで公務員を捉えがちですが、地方公務員として役所に入庁した後はこれらのイメージは覆り、ブラックとも言える労働環境が待っていました・・・
このようなイメージを持った理由として、公務員の仕事をあまり知らないことや、公務員に関する情報にばらつきがあることが考えられます。
役所の公務員の仕事というと住民票の窓口を思い浮かべる人も多いと思います。窓口は空いている時間が限られていますし、住民目線ではあまり大変そうに見えないと思います。また、ネットに出ている情報は公務員と一括りになっていても、実態は職種や省庁、自治体、さらには部署によって全く状況が異なります。ですので一概に公務員全てに共通する情報は無いに等しいです。
この記事では、地方公務員として市区町村の役所にピンポイントをあてて、自分が勤めていた経験などから公務員の労働環境の実態についてまとめています。
データで見る公務員の労働環境
勤務時間
公務員の法定勤務時間は、基本的に1日7時間45分・週38時間45分とされています。これは、民間企業と比べるとやや短めの設定です。
しかし、現場では残業(超過勤務)が多い部署もあり、定時で帰れるとは限りません。
- 国家公務員(令和4年)
- 年間平均残業時間:約220時間
- 本府省(中央省庁)の残業時間:約397時間
- 地方出先機関など:約179時間
特に中央省庁では、夜遅くまでの業務が常態化しているケースも多く、「激務」と言われる理由が数字にも表れています。
- 地方公務員
地方公務員の勤務時間に関する具体的な平均値は公表されていませんが、総務省の労働力調査(平成28年度)によると、地方公務員の月間就業時間は男性で177.1時間、女性で152.0時間と報告されています。これは、全産業平均(男性180.1時間、女性135.7時間)と比較して、男性はほぼ同等、女性はやや長い傾向にあります。
有給取得状況
次に、有給休暇の取得状況です。制度としては、国家・地方ともに年間20日の有給休暇が付与されますが、取得実態は部署や個人の状況によって大きく異なります。
- 国家公務員(令和4年)
- 平均取得日数:15.5日
- 取得率:約77.5%
- 中央省庁に限ると取得日数は13.0日とやや低め
- 地方公務員(令和4年)
- 平均取得日数:12.6日
- 取得率:約63.0%
民間企業の平均取得率(約65%)と比べると、国家公務員は高い水準を保っていますが、地方公務員はほぼ同水準。
特に人手不足の部署や繁忙期には、「休みを取りたくても取れない」状況も起こり得ます。
地方公務員として働いてみた実態
部署ごとに全く異なる「ホワイト」と「ブラック」
公務員=定時で帰れるというイメージは確かに一部では当てはまります。たとえば、住民票などの窓口対応を行う部署では、閉庁後に事務作業がなければ比較的定時退社が可能で、落ち着いた雰囲気の中で働けることもあります。
一方で、生活保護や児童福祉、教育委員会など市民対応が中心の部署では、トラブル対応や相談が絶えず、定時以降にようやく事務作業に取りかかれるような状況も。部署によって「仕事の中身」と「帰れる時間」がまるで違うのが実態です。
私が経験したホワイト部署とブラック部署
私自身、地方公務員として2つの部署を経験しましたが、まさにホワイトとブラックの両極端を体感しました。
最初に配属されたのは企画・総務系の内部管理部門。住民対応はなく、内部職員との調整が中心。残業は月10時間以下で、定時退社が基本という理想的な環境でした。有給も取りやすく、年間で付与される20日間をほぼ消化することができました。
しかし次の異動先は福祉・教育系の部署で、状況は一変。窓口対応と膨大な事務処理に追われ、残業は月60〜100時間。定時を過ぎてからが本当の仕事時間というような生活が続きました。有給もは取れなくはないですが、休んだ後のしわ寄せや周囲の目を考えると気軽に取得できるという環境ではなかったです。私は年度末に退職したのですが、業務の都合で長期の有給消化ができず、3月31日までしっかり(残業もして)働きました・・・
長時間労働の果てに…休職と人員不足の悪循環
ブラックな職場で深刻なのは、これらの業務ストレスから休職してしまう人が少なくないということと、休職者が出ても人員が補充されない点です。誰かが抜けた分の業務はそのまま残った職員に降りかかり、さらに負荷が増す。
この状態が続くと、次の休職者が生まれ、また補充されず…という負のスパイラルが起こります。私の周囲でも、そうした連鎖で職場全体が疲弊していく様子を何度も目にしました。
この負のスパイラルから抜け出すには2~4年毎にある定期的な異動しかありませんが、希望通りの部署に行けるとは限らず、ブラックな環境から抜け出せる保証もありません。
部署の当たり外れが大きいのに加え、異動も“運”の要素が強いという点で、公務員の働き方には想像以上のリスクと不確実性があると感じました。
まとめ
「公務員=ホワイト」というイメージを持ってこの道を目指す人は少なくありません。実際、定時で帰れる日が多い部署や、業務負担が軽い“当たり部署”が存在するのも事実です。私自身も、そういったホワイトな環境を経験しました。
しかしその一方で、長時間の残業、クレーム対応、慢性的な人員不足、そして心身の限界を迎えて休職してしまうような現場も、確かに存在します。福祉・教育などの市民対応業務を担う部署では、「公務員=安定・楽」という先入観が覆されることもあるでしょう。
また、部署異動は避けられず、入庁後にどんな業務を割り当てられるかは“運”の要素も強く、ブラックな部署に配属される可能性もゼロではありません。
大切なのは、外から見たイメージや噂だけで判断するのではなく、職種や部署によってまったく異なる実態があることを正しく理解することです。公務員を目指すのであれば、「ホワイトさ」だけに期待せず、厳しさやハードな一面もきちんと認識したうえで進路を考えることをおすすめします。
「知らなかった…」と後悔しないために、現場の声や実体験から得られる情報こそが、何よりの判断材料になるはずです。